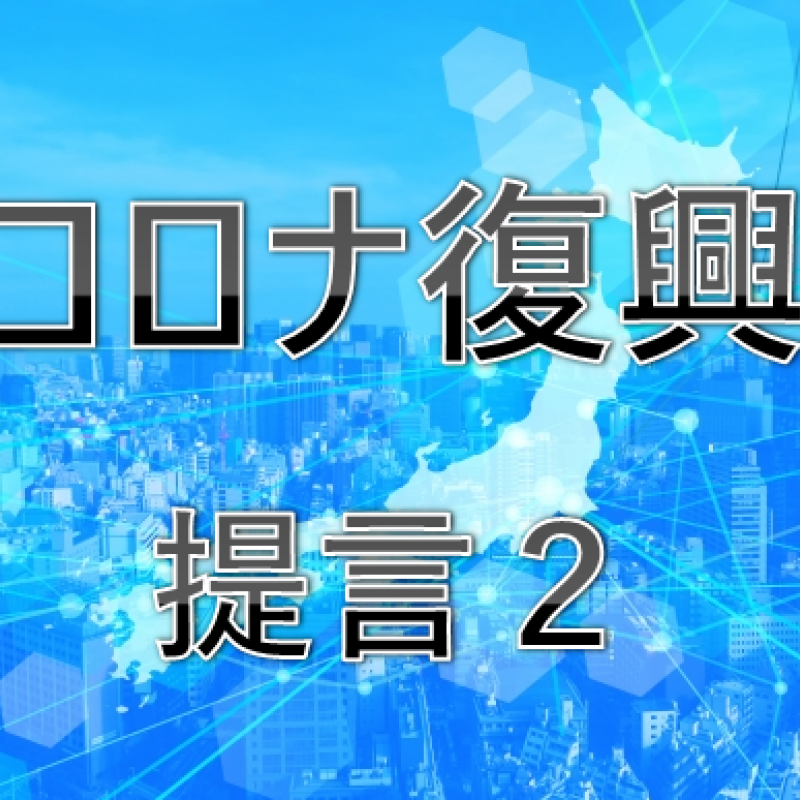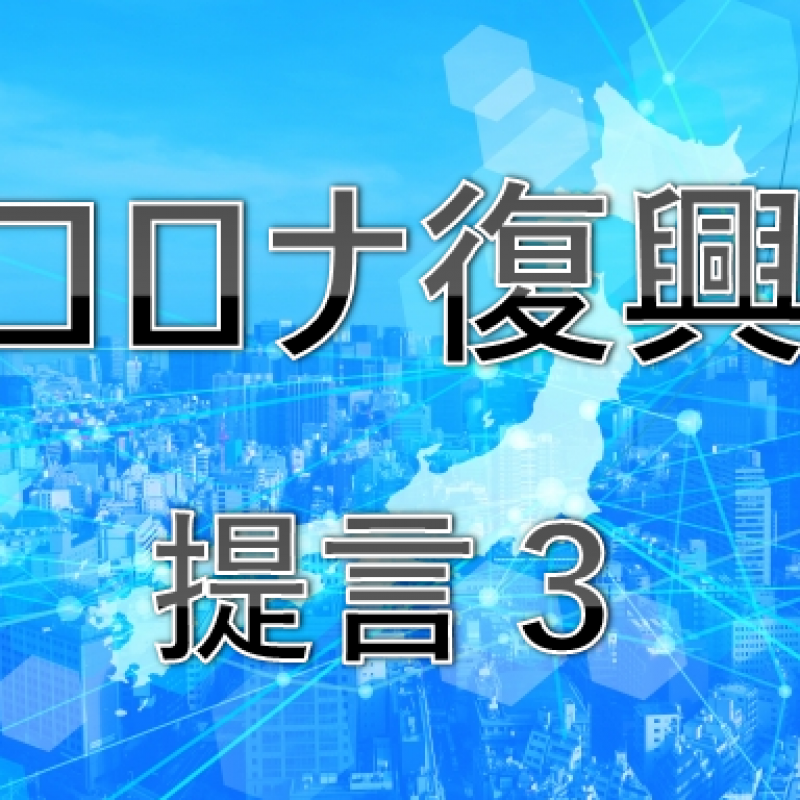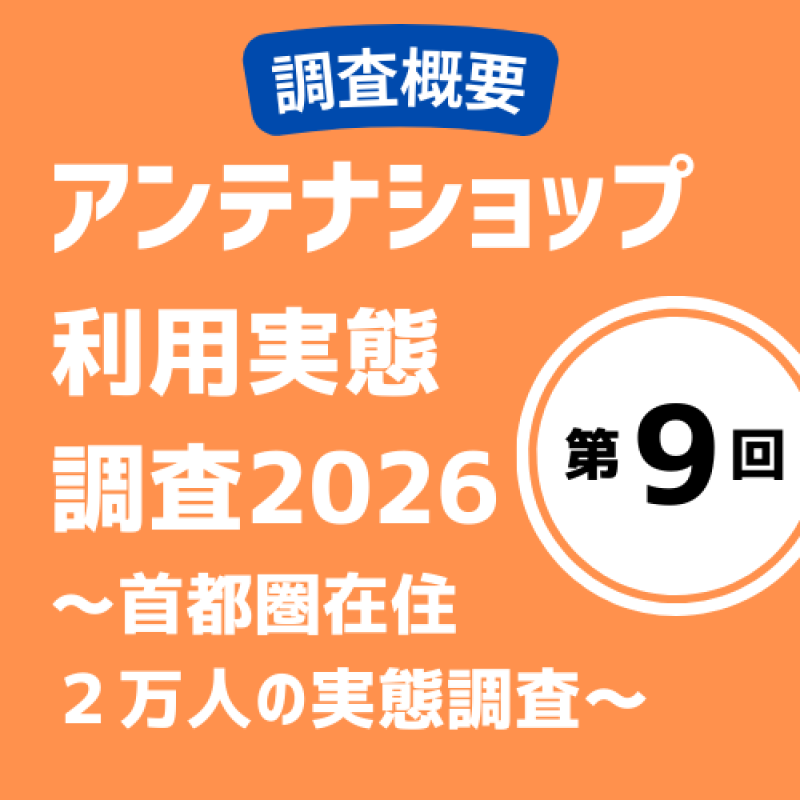消費者の購入額に一定額を上乗せした分の買い物ができるプレミアム付き商品券の発売が話題になっています。政府の平成26年度補正予算に盛り込んだ自治体向けの新交付金を活用して発行されるもので、なんと全国の97%の自治体で発行されるとか。「各自治体での消費拡大につながる」のが目的とのことですが、はたして消費拡大につながるのでしょうか?
「プレミアム商品券」は商品券にプレミアムが付いていますが、これは消費を刺激することにはなりません。日常的な買い物に使える商品券が多いようですが、たとえば1万円に2千円のプレミアムが付いている場合、消費者は2千円多く買おうとするより、1万2千円の買い物をしたときに1万円しか支払わないですむからお得と感じる人が多いでしょう。
特に、スーパーなど日常的な買い物に使えるような商品券の場合は、日頃の買い物で支払うのが現金の代わりにプレミアム商品券になっただけであって、消費額が増えることにはなりません。
東南アジアでは、スーパーなどで日用品や食品を販売する際に、例えば「2つ買ったら1つサービス」などのキャンペーンが多く用いられます。これは消費を1.5倍増やすのではなく、単なる値引きです。購入サイクルが長くなるだけであり、消費拡大にはつながりません。日常的な買い物は、そもそも消費量が決まっているため、消費拡大には簡単につながらないからです。
消費者の金銭的な負担を少なくするから、消費額を高めようというのは、一般的なプレミアム商品券の発行ではだめだということです。
1999年の地域振興券の時も日常的な買い物に充てられることが多かったため、消費刺激効果は期待ほど大きくありませんでした。
では、どうすればいいのでしょうか?
◆特定商品分野や、店舗での活用にすべし
地元商店街や特定店舗でのみ使用できるような商品券にすることができれば、その店舗の活性化にはつながります。また、非日常的な消費につながる特定分野の商品やサービスにのみ使えるようにする方法もあります。しかし、絞り込めば絞り込むほど、商品券としての魅力が薄れることになります。また、発行元の行政とすれば、公平性が失われるような仕組みを打ち出すことはしにくいでしょう。
今回はこうした反省をふまえて、非日常的な消費をうながすため旅行商品を割安で購入できる「ふるさと割」や「プレミアム宿泊券」などの発行も増えています。ただし、たとえば定期的な出張の費用の削減のために「ふるさと割」を使うことになっては、非日常的な消費にはつながりません。これは帰省なども同様ですね。
消費拡大につなげるには、クーポン券を出費が決まっているものに使えるようにするのではなく、そのクーポン券によって新たに消費を創出するような仕組みにすることが必要なのです。
使用範囲や使用者を限定せず、商品券としての自由度を高めることで、その券がオークションで転売される危険も高まります。実際に、オークションサイトでの取引も少なくないようです。
◆制度は実施するのではなく、利用するもの
消費拡大につながる一例として、女性向けの化粧品があります。シャンプーや化粧水などを購入すると、異なるジャンルの小さな新製品のサンプル品がついていることがあります。「お試し」によって新製品の認知度を高め、新しい需要を掘り起こすという狙いです。
地域の場合も値引きするのではなく、まだ認知度の高くない特産品や旅行商品の「お試し」をプレゼントする。その開発に対して助成する、という方法になるのであれば、新たな消費にもつながるし、地元の中小メーカーなどが新たな商品開発をする意欲にもつながるのではないでしょうか。
もちろん、いまの制度の修正なども必要になるため、すぐに実施と言うわけにはいかないかもしれませんが、制度は実施することに意義があるのではなく、地域の活性化のために活用するんだ、ということを忘れないでいただきたいものです。
田中章雄(ブランド総合研究所社長)

プレミアム商品券を、地域の消費拡大につなげるには (田中)
2015年06月06日更新
消費者の購入額に一定額を上乗せした分の買い物ができるプレミアム付き商品券の発売が話題になっています。自治体向けの新交付金を活用して発行されるもので、なんと全国の97%の自治体で発行されるとか。「各自治体での消費拡大につながる」のが目的とのことですが、はたして消費拡大につながるのでしょうか?
この記事のライター
関連するキーワード
関連記事
地域活性化につながる調査や事業に取り組むスタッフを新たに募集。募集職種は調査部(リサーチャー、アナリスト、調査員)、地域振興部(コンサルタント、地域活性化すフタッフ、企画)、および業務アシスタント。また、インターンも併せて募集します。2026年新卒、第二新卒、中途採用で、2026年3月末日締切。募集数は若干名。
公開: 2025-12-29 08:02:27
地域活性化につながる調査や事業に取り組むスタッフを新たに募集。募集職種は調査部(リサーチャー、アナリスト、調査員)、地域振興部(コンサルタント、地域活性化すフタッフ、企画)、および業務アシスタント。また、インターンも併せて募集します。2026年新卒、第二新卒、中途採用で、2026年3月末日締切。募集数は若干名。
公開: 2025-09-01 14:00:00
岐阜県郡上市八幡町で7月15日(土)から「郡上おどり」が始まった。なんとこのお祭り、おどり発祥祭に始まり9月9日(土)のおどり納めに至るまで30夜以上開催される日本一長い盆踊りだ。
公開: 2023-07-19 12:32:24
地域活性化につながる調査や事業に取り組むスタッフを新たに募集。募集職種は調査部(リサーチャー、アナリスト、調査員)、地域振興部(コンサルタント、地域活性化すフタッフ、企画)で、2023年5月末日締切。募集数は若干名。
公開: 2023-04-19 16:13:00
観光庁は観光再始動事業の第1次公募の採択事業139件を発表した。この事業はインバウンドの本格的な回復のために、これまでに一度も実施されたことがないもの等、新規性が高く特別なものを整備し、インバウンドの誘客・消費拡大等につなげるのが目的。
公開: 2023-04-02 20:46:00
最新記事
幸福度や定住意欲度など、地域の持続性につながる指標について調査する「幸福度調査2026」をインターネットにて実施しました。その結果、幸福度は3年連続で低下。前年に引き続き、物価上昇の悩みが高く、6項目の悩みが増加しました。
公開: 2026-02-02 15:28:26
「第9回アンテナショップ利用実態調査2026」は、首都圏(埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県)在住の男女20,000人を対象にインターネットで実施。不完全な回答など信頼性の低い回答を除き、最終的に19,843人から有効回答を得た。本調査では、来店経験やリピート率、購入商品などの店舗利用状況に加え、観光情報の入手、レストランでの飲食、ECサイトの利用など、店舗での商品購入以外の活用状況も分析・収録(約242ページ)。
※本記事では調査結果の一部を抜粋して公開。
公開: 2026-02-02 12:20:02
地域活性化につながる調査や事業に取り組むスタッフを新たに募集。募集職種は調査部(リサーチャー、アナリスト、調査員)、地域振興部(コンサルタント、地域活性化すフタッフ、企画)、および業務アシスタント。また、インターンも併せて募集します。2026年新卒、第二新卒、中途採用で、2026年3月末日締切。募集数は若干名。
公開: 2025-12-29 08:02:27
ここでは、地域ブランド調査2025の都道府県結果のうち、魅力度をはじめ、各主要項目の上位結果について紹介します。
公開: 2025-10-04 23:01:19
地域ブランド調査2025市区町村の調査結果のうち、魅力度の上位50位、主な調査項目の上位結果について紹介します。
公開: 2025-10-04 23:00:00