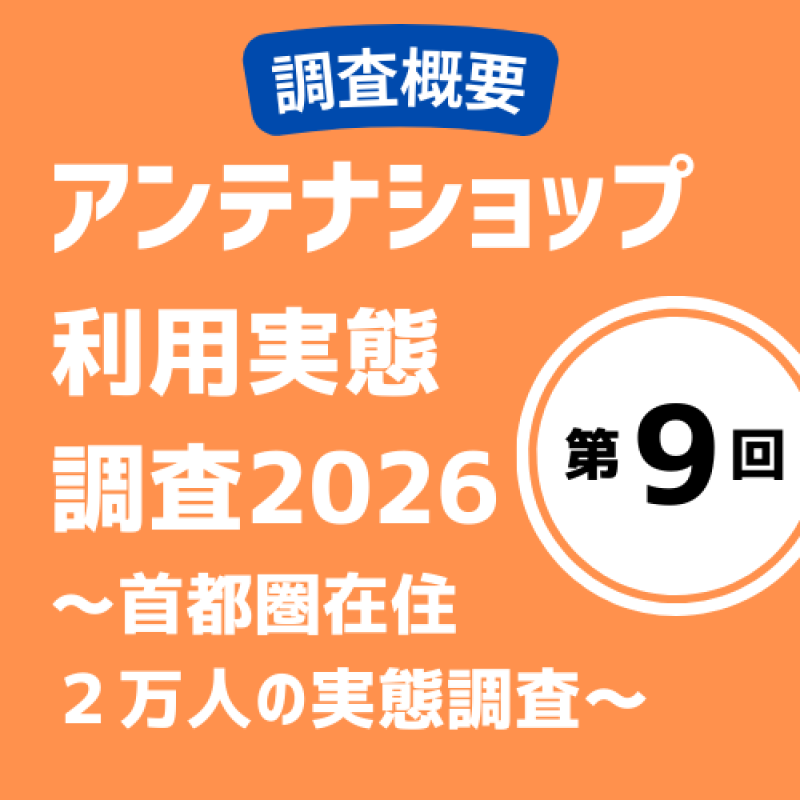猪苗代湖や磐梯山に代表される壮大な大自然
猪苗代湖は日本で4番目の広さを誇る湖で、初めて訪れた人は海かと思うほどの雄大さです。
天を映すほど透き通った水質で、全国でも珍しい「泳げる湖」としても知られています。
百名山にも選ばれている磐梯山(ばんたいさん)は、美しく整った形をしており、「会津富士」とも呼ばれています。山頂からは猪苗代湖や吾妻連峰の絶景を見渡すことができ、登山道も充実していることから、初級者から上級者まで登山を楽しむことができます。
様々な歴史の舞台となった会津若松
幕末に戊辰戦争の舞台となった鶴ヶ城は、難攻不落の名城として有名です。
赤瓦と呼ばれる赤紫色の屋根瓦が特徴で、日本百名城の一つにもなっています。
同じく幕末に会津藩で結成された白虎隊が、戊辰戦争により自刃する悲劇の舞台となった飯盛山。
山の中腹には白虎隊十九士の墓石があり、現在でも多くの人が花を手向けに訪れます。
数々の民芸品や伝統的工芸品
ゆらゆらと揺れる首に愛らしい顔立ちの赤ベコは、会津の民芸玩具として古くから親しまれてきました。赤ベコは平安時代、蔓延した疫病を追い払った赤い牛が由来となっており、今でも厄除けのお守りとして重宝されています。
会津藩主が下級藩士の内職として作らせたことから広まった起上り小法師は、今でも人気ある縁起物の一つです。3センチほどの手のひらにのる大きさで、七転び八起きの忍耐と人生の象徴として愛されています。
美しい光沢が特徴の会津塗は、国が指定する伝統的工芸品であり、気品のある輝きが多くの人を魅了してきました。漆器は多くの職人による分業制によって作られることから、一つの作品は職人たちによる技の集大成といえます。