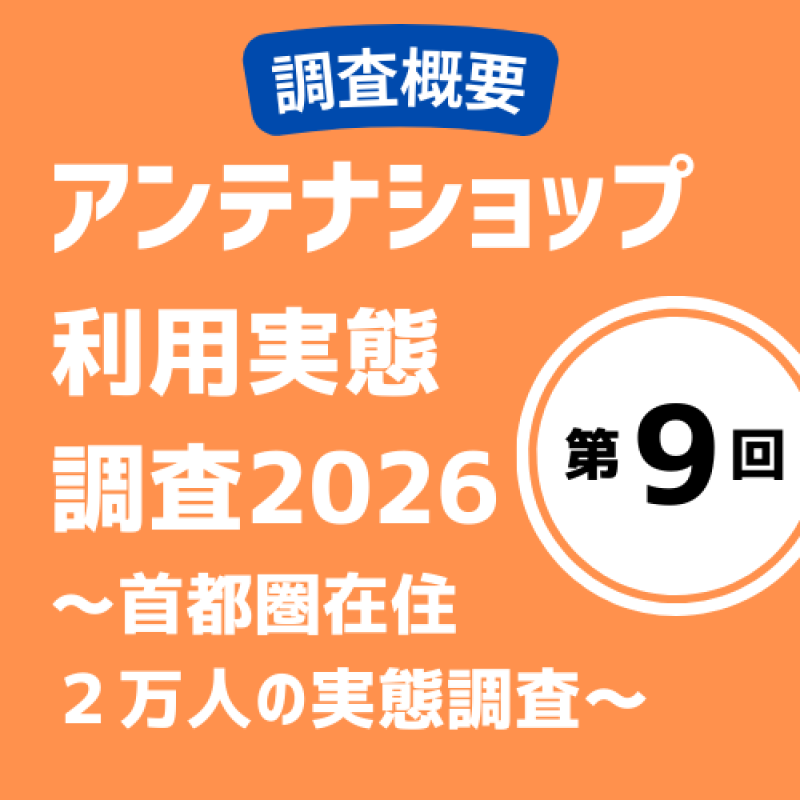下関にはフグ専用の魚市場があり、全国のフグの約8割が集まる。流通しているトラフグのうち天然ものは1割程度で大半は養殖もの。また天然ものの6割は遠州灘沖で漁獲され、下関近海でとれたものは少ない。
他産地のフグや養殖もの、輸入されたフグも下関に集まる。セリなどで売買され、毒がある危険部位を除去する「身欠き」処理された後、東京や大阪などに運ばれる。つまり下関はフグの加工技術の集積地でもある。
江戸時代にはフグの毒で死ぬ人が多かったため、フグを食べることが禁じられていた。明治時代に下関市で全国で最初にフグ食が解禁になり、料理店「春帆楼」がふぐ料理公許第一号となった。その後、下関に多くのフグ料理店ができていった。
なお、フグは「不遇」に繋がり、フクは「福」につながるため、下関では「ふく」と呼ぶ場合が多い。フグの皮をなめして作った「ふく提灯」は下関の特産品になっている。
(ブランド総合研究所社長 田中章雄)

第74回:下関ふく
2012年01月16日更新
この記事のライター
関連記事
人口減少、少子化に歯止めをかけようと、少子化問題に危機感を持ち、子育て支援施策に意欲的に取り組む県により、平成25年4月に発足した「子育て同盟」が、11県知事などの参加による動画「Let It Go~ありのままで~ by子育て同盟」を作成し、インターネット上の動画サービス、YouTubeに公開した
公開: 2014-09-01 23:27:53
ブランド総合研究所世界記録サポート窓口では「ギネス世界記録チャレンジ 自治体パック」サービスを開始した。地域活性化のためにギネス世界記録挑戦を検討している自治体等を対象としたもので、初回の無料相談対応から挑戦記録の提案、申請代行、挑戦当日の立ち会い、挑戦後のアフターフォローまで一貫してサポートします
公開: 2014-04-25 16:57:29
地域ブランドに関する基本的な用語を集めました。日経MJ(日経流通新聞)の2010年7月~12月に、弊社代表の田中章雄が連載コラム「地域ブランドAtoZ」として掲載した記事をもとにご紹介します。
公開: 2014-04-13 18:24:35
日本の各地にある地域産品を紹介します産品名をクリックすると、説明文章のページを表示します。この記事は、日経MJ(日経流通新聞)に「地域ブランド AtoZ」として弊社社長の田中章雄が連載で執筆しているものです。(カッコ内は日経MJの掲載日です)
公開: 2014-03-27 08:39:28
最新記事
幸福度や定住意欲度など、地域の持続性につながる指標について調査する「幸福度調査2026」をインターネットにて実施しました。その結果、幸福度は3年連続で低下。前年に引き続き、物価上昇の悩みが高く、6項目の悩みが増加しました。
公開: 2026-02-02 15:28:26
「第9回アンテナショップ利用実態調査2026」は、首都圏(埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県)在住の男女20,000人を対象にインターネットで実施。不完全な回答など信頼性の低い回答を除き、最終的に19,843人から有効回答を得た。本調査では、来店経験やリピート率、購入商品などの店舗利用状況に加え、観光情報の入手、レストランでの飲食、ECサイトの利用など、店舗での商品購入以外の活用状況も分析・収録(約242ページ)。
※本記事では調査結果の一部を抜粋して公開。
公開: 2026-02-02 12:20:02
地域活性化につながる調査や事業に取り組むスタッフを新たに募集。募集職種は調査部(リサーチャー、アナリスト、調査員)、地域振興部(コンサルタント、地域活性化すフタッフ、企画)、および業務アシスタント。また、インターンも併せて募集します。2026年新卒、第二新卒、中途採用で、2026年3月末日締切。募集数は若干名。
公開: 2025-12-29 08:02:27
ここでは、地域ブランド調査2025の都道府県結果のうち、魅力度をはじめ、各主要項目の上位結果について紹介します。
公開: 2025-10-04 23:01:19
地域ブランド調査2025市区町村の調査結果のうち、魅力度の上位50位、主な調査項目の上位結果について紹介します。
公開: 2025-10-04 23:00:00